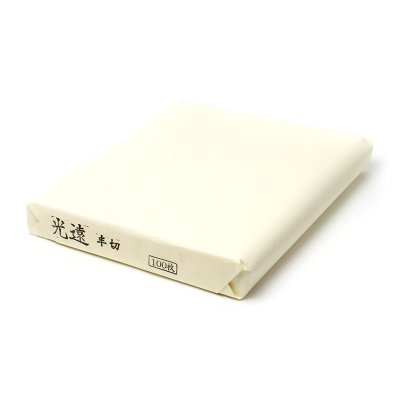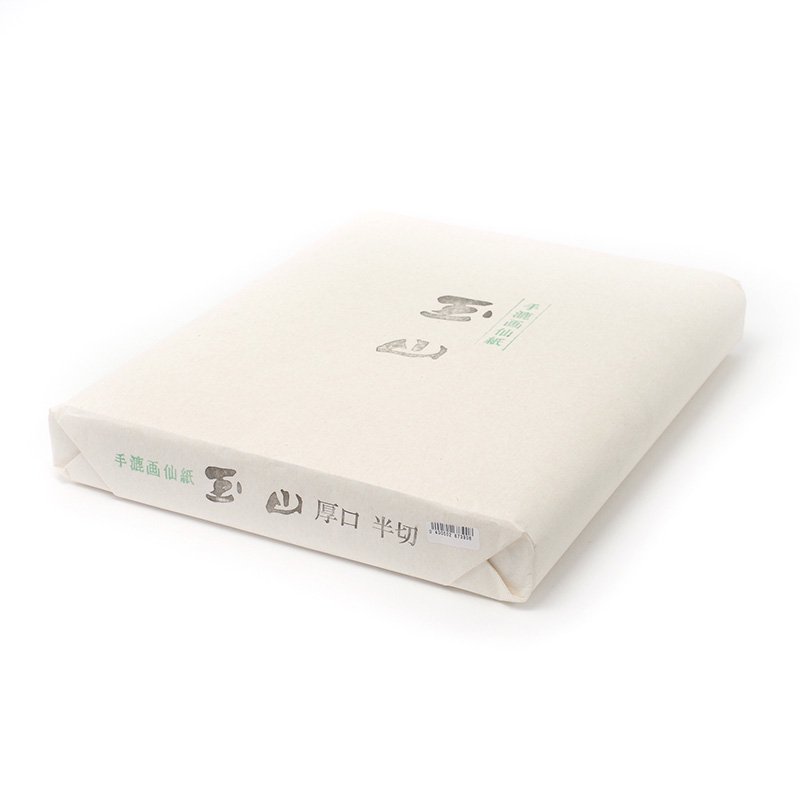��ǯ�ϡ�����Ϥ�褦��
KAKIZOME YOUHIN�������ɸ����ˤ���
������ǯ�ο������Ϥޤ��
ǯ�˰��ٹԤ������ܤ������ֽ��ס�������ʤ�ǤϤν��路�Ǥ���ï������٤��θ��������Ȥ�����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
��ǯ�λϤޤ�ϸ�ö�ˤ���ޤ���ǯ���ˤϲ�������ݽ����ꡢ�����������ν����ʤɡ���ǯ��ޤ��뤿����͡��ʻ��٤�Τ����ܤ������Ǥ���
�Τ������ܤǤϤ������Τ˿����ɤ�Ȥ����ͤ������ꡢ�������ͤ����ǤϤʤ�����ǯ���������Ƥ�������п��ͤ�ޤ�����٤뤳�Ȥ����ڤˤ���Ƥ��ޤ�����
��������ڤ˻Ĥ��Ƥ����������ܤ������ΰ�Ĥȸ����뤫�⤷��ޤ���
��Ӥȴ��ա���ǯ��̵���ꤹ�뤳�ȡ�
������ǯ�λϤޤ�
�ֺ�ǯ�Ϥ����ǯ�ˤ������ʡסֺ�ǯ�Ϥ����������Ȥ뤾�פȤ����褦�ʼ�ʬ����Ǥ���ɸ���դ⿷����ǯ�λϤޤ�ˤ����Ǥ��Ƥߤ�Τ⤤����ΤǤ���
��ǯ�����餳���פ����ȡ��ꤦ���Ȥ�ï�ˤ⤢��Ϥ��Ǥ����ꤤ����դˤ��롣������ǯ�λϤޤ��ĩ�路�ƤߤƤϤ������Ǥ��礦��
��ʬ�λפ���ʸ������Ȥ������Ȥϰճ������ڤǤ�����ʬ�λפ���ʸ���ˤ��뤳�Ȥϡ���ʬ�ο��˹�ळ�ȤǤ��ꡢ����ƿ������ռ����뤳�Ȥˤ�Ҥ���ޤ���
���ʤ���ʸ�������Ȥ����Τϸ���ĤĤ���ޤ�������ɮ�ǽƤߤ�Ȥ�����̴�����������Ϥ��Ǥ���
��²��ͧãƱ�ΤǤ��ߤ��ο�ǯ����ɸ������ˤĤ��Ƹ��ʤ��顢������ˡֽ��פ�ڤ���ǤߤƤϤ������Ǥ��礦����
�����
��������
���ε�����ʿ�»���ˤޤ��̤�ޤ���ʿ�»���ε���Ի��Ǥ���ֵȽ�Ϥ�פ����ε����Ȥ���Ƥ��ޤ���
�ΤϽ�ƻ��Ȥ������Ϥ�ɮ�Ȼ椬�Ȥ��Ƥ��ޤ�������ö��ī�˵��������ʿ��Ȥä��Ϥ���뤳�Ȥ˻Ϥޤꡢ����ǯ��ǯ���ͤΤ�������˸����äƽ˲����Τ�����Ȥ˻Ϥޤä��Ȥ���Ƥ��ޤ���
�Το͡�����ɮ��ʸ����Ȥ������ȤϺ����⤺�äȽ��פʰ�̣����äƤ����Ϥ��Ǥ����������˽뤳�Ȥϡ��ΤοͤˤȤä��ڤʤ�ꤤ���ä��Τ��⤷��ޤ���
���ξ�ã���äƿ��ͤ˽�����Ǽ���뽬�路�������ޤ����ڤ˼����Ѥ���Ƥ����ΤǤ��礦�����ְ���Ū�ʹԻ��Ȥʤ�ΤϹ��ͻ��夫����ȸ����Ƥ��ޤ���
����ΤϤ��ġ�
���Ȥ����Ȥ�����������Ǥ������ºݤϤ��ĹԤ���ΤʤΤǤ��礦����
�����1��2���˹Ԥ���ΤȤ���Ƥ��ޤ��������Ҥ䤪�����Ƽ����Τ����Τʤɡ��͡��ʾ��ǹԤ��Ƥ��ޤ��Τǡ����ˤ��⤽�줾��ˤ�äưۤʤ�ޤ���
������Ȥ����Τ�Ϥä���Ȥ������֤���ޤäƤ��ʤ��褦�ˡ�������˹Ԥ���Ȥ������Ȥ�����Ǥ������Ϥä���Ȥ����������ꤵ��Ƥ����ΤǤϤʤ��褦�Ǥ���
�Ǥ��Τǡ������ޤ����ϰ��Ĵ�٤Ƥ����������ꡢ�⤷�ԤäƤߤ������������Ĵ�٤Ƴ�ǧ���Ƥ����������ۤ��������Ǥ��礦��
����Ԥ����ҤǤ���С���ؤΤ�����Τ��ȤˤǤⵤ�ڤ˽��Ƥߤ�Τ⤤�����⤷��ޤ��������ơ�������λ���������˹Ԥ��Ƥ��뤳�Ȥ�¿���褦�Ǥ���
��������
������ι���֤ɤ�ȾƤ���
������˽����ϡ֤ɤ�ȾƤ��פ�dz�䤹�Τ��ҤȤĤ���ˡ�Ǥ���
������������ˡ����������䤪���ʤɤ��dz�䤹�֤ɤ�ȾƤ��פȤ����Ի�������ޤ���
�֤ɤ�ȾƤ��פϤ���ǯ��̵��©�Ҥäƾ�����Ǥ���1��15�������������ϤǹԤ���Ի��Ǥ���
���������Ϣ��ʤ���ʤ�ˤ���ꡢ���ʤɤ�ƲȤ��������ꡢ�ڤ��ΤǺ�ä��䤰����Ѥ߾夲��dz�䤹�кפ�Ǥ���
�֤ɤ�ȾƤ��פǽ���dz�䤷���椬�⤯�夬��л�����ã����Ȥ��������⤢��ޤ�����dz�䤷����˾�ä�ǯ���ͤ�ŷ��������Ȥ⤵��Ƥ��ޤ�����
����֤ɤ�ȾƤ��פ�dz�䤷�ư�ǯ��̵��©�Ҥ�ꤦ�Τ��ɤ������Ǥ���
�����ޤ����ϰ�ˤ�äƤ�������ۤʤ뤫�⤷��ޤ���Τǡ�Ĵ�٤Ƥ����Ȱ¿��Ǥ���
�ޤ������ҤʤɤǤ�Ť���Ƥ��뤳�Ȥ�����ޤ��Τǡ�����ο��ҤιԻ����ǧ���Ƥ������Ȥ褤�Ǥ��礦��
���˻Ȥ���������
�ֽ���ƻ���켰�Ѱդ�������ɡ�����Ф����Τ�Ǻ��Ǥ��ޤä��פȤ������Ȥ�褯���뤫�⤷��ޤ���
���ޤ����ͤ��ʤ��Ƥ⡢�ޤ��Ͽ�ǯ��ˬ���ˤ�ʸ����Ƥߤ�Τ���������Ǥ���
�ޤ�����ǯ���������ɸ�ʤɤ�ʸ�ϤǤ⤤���Ǥ�����üŪ��ɽ�����ͻ��ϸ줬��ή�ˤʤäƤ���褦�Ǥ���
����Ǥ������դ俷ǯ������˹礦���դ����֤��Ȥ�ޤ��ڤ��ߤΰ�ĤǤ���
������ǯ��ޤ�����դ�ɽ���ͻ��ϸ�䡢��ǯ��ˤ�����Ǥ������ܸ�ʤɡ��ڤ��ߤʤ�������Ǥߤ�Ȥ褤�Ǥ��礦��
������ʤɤǤϡ����ܤ���ޤäƤ���Ȥ����⤢��ޤ�������ͳ�����٤�Ȥ����⤢��ޤ�����������ȤǤ������ϼ�ͳ�Ǥ���
�������Ӥ�Ǻ�����ˤ⡢���ˤԤä���Τ���Ǥ������դ�Ҳ𤷤ޤ���
��̣���Τ�С����դξ�ʤ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����顢�ڤ��ߤʤ�����Ǥ������Ǥ���
�Ҷ������ν�����
2025ǯ�δ��٤ǡ������ͤˤ�����Ǥ���
�ߤΤꤢ��ǯ�ˤʤ�褦����ǯ�ﵯ���ɤ����ա�
�Ԥ�˾��Ǥ������Ȥ��¸������̣������ޤ����ޤ����ۤ��������ξ��֤���ǯ�����ʤ����ޤ���
�礭�ʤ�����������������Ф������ʴ�˾��ɽ���ޤ���
��ʡ������äƤ��롣��ʪ���Ѥ߹���������Τ��ȡ�
���ؿʤࡢ��ɸ�ʤɤ˶�Ť��ʤɿ�ǯ�������Ȥˤդ��路�����դǤ���
�����������
ʩ���ʤɤǤ�Ǥ��������Ȥ��Ƹ�������
���ۤζ���̤꤫���ä������Ф��֤˸����뵤�ݸ��ݡ�
��Ǥ������ȡ���ʡ���˱ɤ��̣������ա�
Ĺ������ڤ��ळ�ȡ�
¿���ι�ʡ����ʡ��¿�����ȡ�
˭���ǡ��͡�����餷��ڤ��ळ�ȡ�
���٤�ʷ�ϵ��˰Ҹ����������դ��Ω�ɤ��ͻҤ�ɽ����������ĩ�路����ǯ�ˤ������ᡣ
���ܤˤ����Ʒݻ���ʸ����ȯŸ���ʲ����Ƥ�����¤Ū�ʲ����Υ١����ȤʤäƤ�����ۡ�
��Ǥ�����ΤȤ��ƷĻ����Ⱦͤ˻Ȥ��뿷ǯ�ˤդ��路�����ա�
���˿��˷��֤�Ǹ�ޤǴӤ��̤����ȡ� �ֽ�֡פϻפ�Ω�ä��Ȥ��κǽ�ε��������֡� �ִ�Ű�פϤ���̤����Ӥ��̤����ȡ�
���ˤ�������λ�
����Ū�ʡ�Ȭ���ڤ�ץ�����
����ѻ�Ȥ��äƤ⡢��Ĥη�ޤä������������ǤϤ���ޤ������Ѥ������ˤϼ¤Ϥ����Ĥ��Υ�����������ޤ���
��Ǥ���ɽŪ�ʤ�Τ���Ȭ���ڤ�ʤ�Ĥ���ˡפȤ����礭���λ�Ǥ���
Ⱦ��������Ϻ٤���Ĺ�����ܤۤɤ����礭���Ȥ����Х���������䤹�����Ȼפ��ޤ���
��Ȭ���ڤ�פȤ����Τ������1/8�ˤ����������ǡ����Τ��Ȥ����Ȭ���ڤ�פȸƤФ��褦�ˤʤ�ޤ�����
����ʤ��ˤȤ�����ʹ������ʤ����ˤȤäƤ������ߤΤʤ����դ��⤷��ޤ�����ƻ�λ�ˤ����ƺǤ���Ȥʤ��礭���ǡ���69��136cm�ۤɤ��뤫�ʤ��礭�ʻ�Ǥ���
�ɤ�ʥ������λ��Ȥ����ϡ��ϰ�����Ԥ������Τˤ�äƾ������İ㤤�ޤ����ɤ��ν��Ǥ����Ū�褯�Ѥ�����Τ�Ȭ���ڤ�Ǥ���
Ȭ���ڤ��¾�ˡ�Ⱦ���Ȥ��ޤ�����Ⱦ�ڤȤ�������礭��λ��褯�Ȥ��Ƥ��ޤ�������ѤȤ������̷�ޤä�������������櫓�ǤϤ���ޤ���
�͡�������Ǥ褯�Ȥ���Τ���Ȭ���ڤ�ץ��������Ȥ������ȤǤ���
���ޤ��礭���ȽΤ����ѤǤ�����Ȭ���ڤꥵ���������ˤϤ��礦�ɻȤ��䤹���������ʤΤ��⤷��ޤ���
�äˤ˽�������प���ͤˤȤäƤ�Ⱦ��������Ĺ����ϥ������䤹���礭���Ǥ���
��ͤ����Ǥ��������ޤ�������ʸ��������ˤȤ�äƤϡ�Ⱦ���Ⱦ�ڤʤ������Ѥ˻������Ǥ��������Τ��ĤǤ���
������ʤɤ˻��ä�����ϡ�����Ⱦ�極�����˹�碌��ɬ�פ�����ޤ����������Ǥʤ����ϡ�Ȭ���ڤ�ץ�����������Ū�Ǥ���
�������Ⱦ�ڤʤɤ˻פ�����Ƥ⡢Ⱦ��˽Ƥ����ꤢ��ޤ���
��ͷOnline��������λ�
��ͷ�Ǥϡֽ�ƻ���֡סֳ�����˱�פʤɤ�Ȭ���ڤꥵ���������ᤷ�Ƥ��ޤ���
�ֽ�ƻ���֡פ����ߤˤ����Τǽ鿴�Ԥ��ä�������ˤ�������Ǥ���
�ֳ�����˱�פ����ߤ��Ф���Τ��������Ԥ����ˤ������ᤷ�Ƥ��ޤ���
���줾�춦�ˡ�Ȭ���ڤꥵ������Ⱦ�極�������Ѱդ��Ƥ��ޤ���
���ˤ��������ɮ
���ǻ��Ѥ���ɮ�ϡ����ʻȤ���ɮ�����礭���Τ���ħ�Ǥ���
ɮ�ˤϹ��������ޤ�����������ˤ�äƵ��ʤ��ۤʤ�ޤ��ΤǤ����Ӥ��������ݤ�ɮ��������礭�������֤��Ȥ����ᤷ�ޤ���
�ɤΤ��餤���礭����ʸ���������������ɮ���礭�����Ѥ�äƤ��ޤ���
����Ū�ˡ��礭�ʻ��ۤ�������礭��ɮ��ɬ�פǤ���
�ޤ���̾�����Ѥκ�ɮ��˺�줺���Ѱդ������Ȥ����Ǥ���
��ͷOnline���������ɮ
Ȭ���ڤ�Ⱦ��ˣ�ʸ������ɮ�ϡ���19��70�Сװ̤���¤�ʪ����������Ǥ���
���줯�餤��ɮ�Ǥ�����ϴޤߤ��ɤ����٤��Ϥ��դ������˽����Ǥ��ޤ���
ɮ�ν��餫���ϡ�����ɮ���ӤȹŤ��Ӥ������äƤ���ɮ�ˤ���������Ǥ���
�㿧�����ӤΡ�������ϹŤ���ӤǤ��Τǥ��㡼�פ�����������ˤ�������Ǥ���
̾�����Ѥϡ�����������ǭ�����Ρֶ��ںԡפ⤦�����¤�ʪ�Ǥ�����־Գ��פʤɤ��䤹���͵�������ޤ���
������ʤΥ��ƥ��Kakizome Item Category
������ʤƥ���̤ˤ����⤷�Ƥ��ޤ���
���ʹʤ���߸���
�� [0] ������ [1-0] ���ʤ�ɽ��
���ʥ��ƥ���Item Categroy
�Ķȥ�������Shop Calendar
| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |