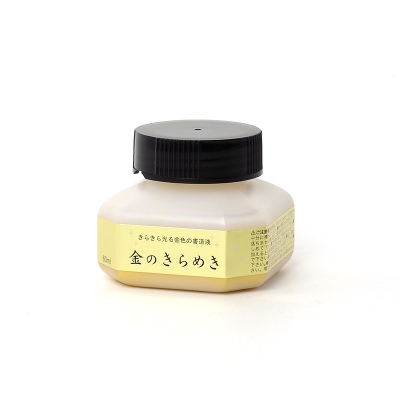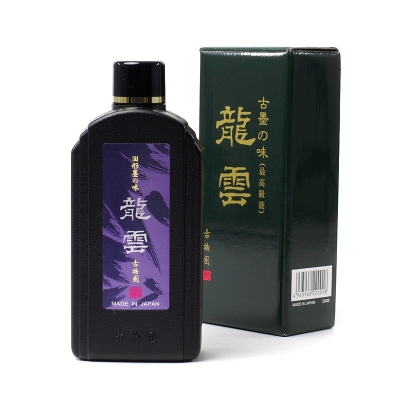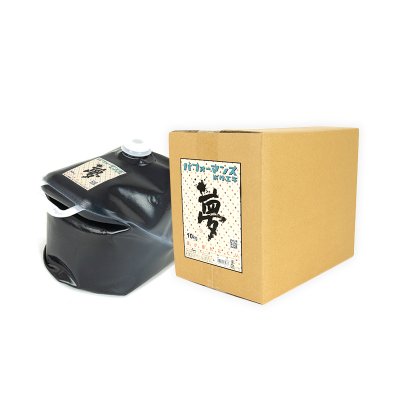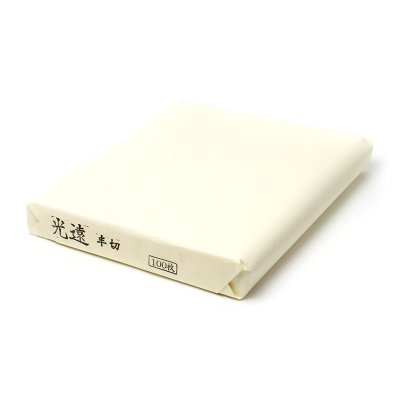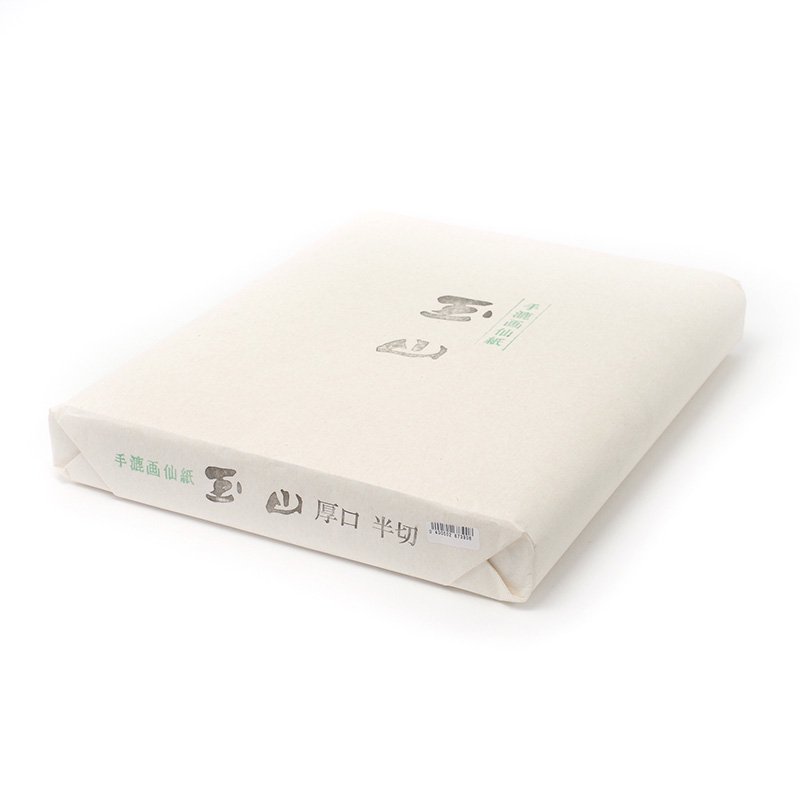�ϱ�
BOKUTEKI�ڽ�ƻ���������ϱա��Ͻ��ۤ�250���ʾ��갷����
�����ѡ������ѡ������Ѥ�Ϥ��ᡢ���ϡ��̷С���ա����ϡ����Ϥ���ѥե����ޥ��ϱդʤ�˭�٤ˤ������ޤ���
�����å����ü��Ϥ⤢�ꡢ�����������Ȥ����ޤǡ�����������ʸ���������ޤ���
������٤������������ޤ���
��ڤ˽��������ϱ�
�ϱդϡ����������ȯ�Ƥ���Ƥ��麣���ޤǡ�¿���οͤ˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
������ˤ�äƤ��Ͻ��Ȥ�ƤФ�Ƥ��ޤ��� �ϱդˤ�籷ϡ�����Ϥ��������Ӥˤ�äƻȤ�ʬ����ɬ�פǤ���
��ͷOnline�Ǥϡ���Ƹ�������顢��ɮ�����ʡ��������ʸ������ϱդޤ��͡��ʾ��ʤ���·���������ĤǤ⤪�㤤�����ʤǤ��������������ޤ��Τǡ����Ҥ�������������
�͡��ʤ��ϱդ��ƽ�ƻ��ڤ��⤦
��ǯ�Ǥϡ����泫ȯ���Ԥ��Ƿ��Ϥ�ɽ���Ϥ˶ᤤɽ������ǽ�ʾ��ʤ���������ϱդʤ��͡��ʾ��ʤ����䤵��Ƥ��ޤ���
����ɽ���Ϥΰ㤤�����ᤷ�ơ����ʺ���ڤ���Ǥ���������
�ϱդ�����
�ϱդΥ��ƥ���Bokuteki Category
���Ӥˤ��碌���͡����ϱդ���ȯ����Ƥ��ޤ���
�����Ȥ�ɽ���ˤ��ä��ϱա��Ȥ��䤹���ϱդ�õ���������������ޤ���
�ϱդ�����Bokuteki Fluid Capacity
�ϱդΥ֥���Bokuteki Bland
��ͷOnline�Ǥ�Ϸ�ޥ�������ϱդ��갷�äƤ���ޤ���
�Ͻ����ä��ֳ��������ɤ�Ϸ�ޥ�������ϱ�Ʋ�סָ��ݡסָ��߱�ס����ʼ�����ʤμ��ҥ֥��ɾ��ʤޤǡ������μ��फ�餪���Ӥ��������ޤ���
�ϱդ���������Tag Search
�ϱդΥ����Bokuteki Colum
�ϱդΤȸǷ��Ϥΰ㤤
�ϱդȸǷ��Ϥϰʲ�����Ĺ������ޤ���
���Ƿ��Ϥ�Ĺ��
�����ߤ��Ͽ���Ф��٤ˤϷи���ɬ�ס�
���Ф��ޤǤ��Ϥ������֤�ɬ��
���Ͽ��˱��Ԥ����Ф뎡��Ω��Ū��
�����������������Ф��䤹����
��ɽ��κݤ�ή�����������㤤��
��ɮ������������������㤤��
��Ĺ����¸����ǽ��
���ϱդ�Ĺ��
�����٤˹��ߤ�ǻ�٤��ϱդ������롣
���Ϥ������֤�����Ǥ��뎡
���Ͽ��˱��Ԥ����Фˤ�������ʿ��Ū��
�����������������Ф��ˤ�����
��ɽ��κݤ�ή�����������⤤��
��ɮ������������������⤤��
����¸���֤�û��������ǯ���١�
�ϱդȸǷ��ϰ㤤�θ���
�ϸǷ��Ϥ��ϱդΰ㤤�Ͼ嵭���̤�Ǥ��������ʼ����ϱդ������ȳ�ȯ����Ƥ��븽�ߤǤ� ���Ƿ��Ϥ�Ȥ����ɤ��ΤϲäƤ��������ɡ��Ĥ����������Ȥ������Ϥޤ��ޤ���¿������ä��㤤�ޤ���
�����װ��Ȥ��Ǝ��Ϥ���������ɤ��˷�ޤäƤ��롣���Ȥ����ռ����������Ĥ���Ƥ���Ȥ������Ȥȡ��ϱդ�����ʿ��Ū��̣�襤���ʤ��Ȥ����Ƥ��뤳�ȤǤ��礦���ǤϤɤ������ϱդ���Ƿ��Ϥ��ɤ��ΤǤ��礦����
�ϱդΥޥ��ʥ����ǤȤ��Ƽ��夲���롢��ʿ��Ū�˸������ ��ͳ�ΤҤȤĤȤ��Ƥϡ����ϱդ�γ�Ҥ��Ƥ�����פȤ������ȤǤ���������ϸ���Ǥ���
��ȯ������ϱդϤ����Ǥ��ä���ǽ���Ϥ���ޤ��������ߤǤϲ��ɤˤ����ɤη�̡�����Ū�ʤθǷ��Ϥ�γ�Ҥ��礭���� 0.2��0.6�ώ����ێҎ��Ď٤��Ф��ơ��ϱդ�γ�Ҥ��礭���ϡ�0.08��0.3�ώ����ێҎ��Ď� �Ȥ����Ƥ��ޤ��� �ʢ� 1�ώ����ێҎ��Ď� �� 1�Ф� 1/1000�ˤĤޤ��ϱդ�����γ�ҤϺ٤����ʤäƤ���ΤǤ���
�ǤϤɤ������ϱդǽ줿ʸ����ʿ��Ū�˸�����ΤǤ��礦����
����ϡ��Ƿ��Ϥ�����Ϥ����٤��ᤵ�䰵�Ϥʤɤˤ�äƥ�餬�Ǥ��뤳�Ȥˤ�ä�γ�Ҥ��礭�����͡��Ȥʤꡢ������ȿ�ͤ���Ω��Ū�˸�����Τ��Ф����ϱդ�γ�Ҥϵ����������碌���뤳�Ȥˤ�äơ�γ�Ҥ��礭�����Ѱ�ˤʤäƤ��ޤ�������Ȼפ��ޤ���
�������Ƿ��Ϥ��ϱդΤɤ��餬�ɤ��Τ��Ȥ������Ȥϡ�ɽ����ˡ���¤�ʤ������äƤ��븽�ߤǤ����˺���Ǥ���
���Ȥε���ɽ����ˡ����ǡ����٤����Ӥ���������
籷Ϥȼ���Ϥΰ㤤��������
籷��ϱդȼ�����ϱդΤ��줾�����ħ�ϰʲ������ޤ���
��籷��ϱդ���ħ
1.������μ������Ͽ������뤳�Ȥ�����뎡
2. ��������Ϥο��Ӥ����뤳�Ȥ�����뎡
3. �վ��֤��ݤİ١��˥���θǤޤ��������ޤ��� ����ʬ�����ޤޤ�Ƥ��ޤ���
���ΰ١�ɽ���Ԥ��ޤǤδ�����֤Ȥ��ơ��� �����֤��פ��ޤ���
��������ϱդ���ħ
1. ɽ��κݡ��˥��ߤ�ȯ�������ǽ�����㤤��
2. �϶�����ɽ�����䤹����
3. ������μ������Ͽ��俭�Ӥ����뤳�Ȥ�����
���줾��λ��Ѥκݤ�������
�ϱդˤϡ��� 籡ʥ˥���ˡ٤���Ѥ�����Τȡ��� ���� �٤���Ѥ�����Τ�����ब���ꡢ���줾���Ĺ���û�꤬����ޤ���
ɽ����ˡ��ǻ�٤ˤ���ϱդ�����Ϥ�������ϱդ�����������ĺ������Ǻ������ɽ���ԤäƤ���������
ǻ�ϱդ����Ϥ�����Ƥ����Ѥˤʤ�����ˡ��ɥܥɥܤ��ϱդ����Ϥ����줿��˿�㡼������ƥ����äȤ�����������
�����Ť��ϱդ����Ϥ�����ƤϿ�����Ƥ��������Ĥ��֤��Ԥ��褦�ˤ��Ƥ���������
�ϱդȿ夬���ä���Ⱥ�������ʤ��ޤޤ˽�ޤ��ȡ���ʬ�ˤ�ä�ǻ�٤��ۤʤ�١�ɽ��κݤ�ή����ǽ�����⤯�ʤ�ޤ���
ɽ���Ԥ��ޤǤδ�����֤ϡ���� �ϡ١ʴ������ ������ɬ�סˡؼ���ϡ١ʴ������ ��������ɬ�ס�
�ȤʤäƤ��ޤ���
���嵭������֤Ϥ����ޤǤ��ܰ¤Ǥ�����¸���֤伾�٤ˤ�äƤ���֤��Ѥ�äƻ���ޤ��ΤǤ����դ���������
�ޤ����ϱդ����Ϥ�����Ƥ����Ѥ������ϡ�����ϱդ��褯������褦�˽�ʬ�ˤ��������Ƥ����Ѳ���������ǻ�٤ΰ㤤�ˤ��ɽ����˥˥��ߤ������ޤ����ˡ�
�ϱդλ��Ѵ��¤ˤĤ��Ƥ�����
�ϱդˤϻ��Ѵ��¤�����ޤ������ʤˤ�äưۤʤ�ޤ��Τǡ����դ��ޤ��礦��
��Ƹ�����ϱդʤɤλ��Ѵ��¤�Ĺ��ǡ�2~3ǯ�Τ�Τ⤢��ޤ�����ŷ��籤��ü���ˡ�Ǻ��줿�ϱդ�1ǯ��û����ä��ꤷ�ޤ��Τǡ����ѽ���ɤ�Ǥ����Ѥ���������
�ϱդδ�Ϣ����ƥ��Bokuteki Contents
��ͷOnline���ɤ�ʪ�Ǥ��Ҳ𤷤Ƥ����ϱդ˴ؤ��뵭����ޤ�����
�ϱ� ���ʰ���Item List
���ʥ��ƥ���Item Categroy
�Ķȥ�������Shop Calendar
| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |