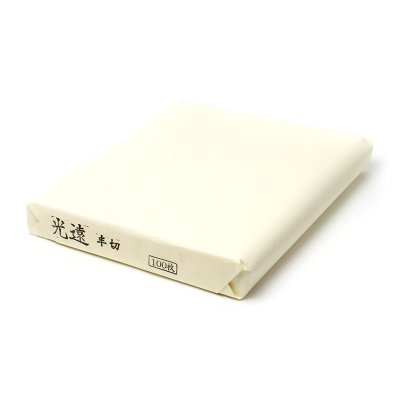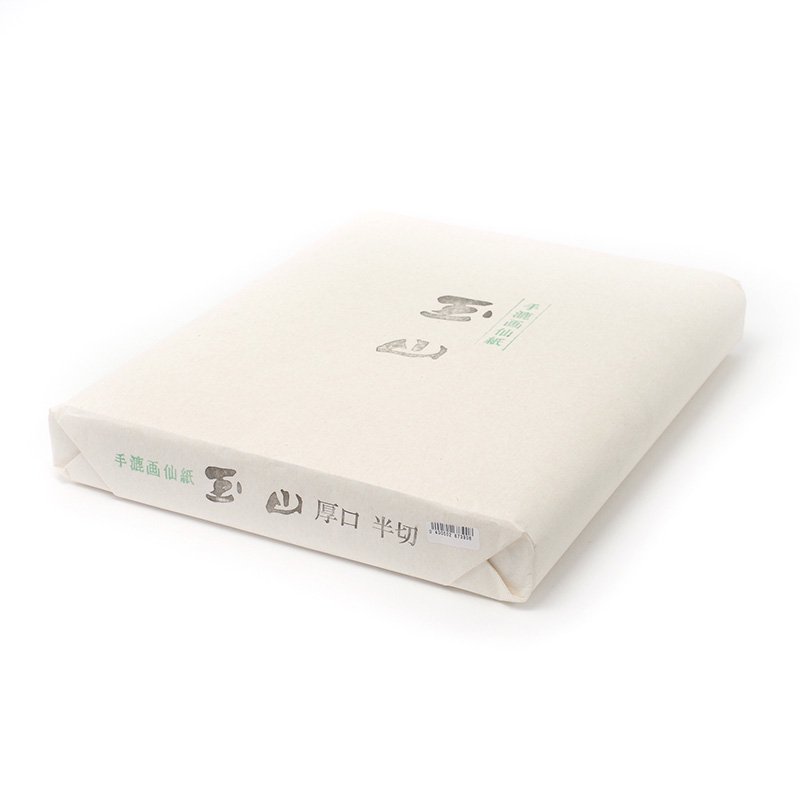墨磨り機
SUMISURIKI文明の利器を使う
書道展に出展する条幅作品などの大作を書く場合は沢山の墨が必要になります。
そんな時におすすめなのが、墨磨り機です。
固型墨を使用するとやはり思い通りの墨色やニジミを出せますし、とても経済的です。現在では書家や学書者の方々の間で広く使用されています。
書遊では墨運堂・呉竹・古梅園製の墨磨り機を取り扱っています。
墨磨り機の選び方もご紹介していますので、ぜひ一度ご覧ください。
おすすめの墨磨り機
色々あるけれどどれを選べば良いのか分からない、どう違うの? そんな方の為に、墨磨り機をご紹介します。
1.微粒子の磨墨液を短時間で磨りたい方
「墨磨り職人 墨運堂製」
1丁掛けの漢字用墨磨り機。
墨磨り機は粒子が粗くなってしまうといわれていましたが、硯を斜めにすることにより改善された商品です。硯板が斜めのまま回転するので、墨と硯板が面ではなく点で接します。これにより過重が集中して、細密な硯面と併さり早く磨れる訳です。硯面が斜めにセットされている為、墨が水に浸かり続けることがなく、墨のひび割れやふやけを防ぐことができる墨磨り機です。
墨池斜硯が「漢字用」「かな用」「天然石」と3種類販売しているので、用途に合わせて使用することが可能です。
・漢字用は1回の墨磨りで、約30〜40mlの磨墨液をつくる事ができます。
約2時間で超濃墨の状態になります。
・かな用は1回の墨磨りで、約5〜15mlの磨墨液をつくる事ができます。
約30分で超濃墨の状態になります。
2.微粒子の磨墨液を沢山磨りたい方
「スーパー墨磨り機 TK-N型」
墨磨り職人の技とを兼ね備えた、2丁型の墨磨り機!
一度に60〜80mlの磨墨液をつくる事ができます。
墨池斜硯は「超微粒子人口硯」と「天然石」の2種が使用できます。
3.もっと沢山磨りたい方
「墨磨り機るんるん 古墨園製」
2丁掛け墨磨り機です。和墨の場合180ccを約60分で磨りあげます。
一度に最大で180ccの墨液を得ることができます。
硯面の高さ調節が可能で、約60cc/約100cc/約180cc と3段階で磨り分けることが可能です。
万が一硯面が磨り減った場合でも、セラミック板に専用砥石をかけることで継続してお使いいただける商品です。
墨磨り機の使い方
墨磨り機は墨をセットして墨池斜硯に水を入れておくだけ。
できあがったら磨墨液を水でお好みの薄さに薄めて使用してください。
磨墨液がトロトロ状態になるまで磨りこんでいただきますと、より効果が発揮されます。
墨磨り機 商品一覧Item List
全 [14] 商品中 [1-14] 商品を表示
商品カテゴリItem Categroy
営業カレンダーShop Calendar
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |